※この記事はアフィリエイト広告を利用しています。
こんにちは、ナノハです。
子育てって大変ですよね。特に男の子は「なんで、こんなバカなことするんだろう」「なんで言うことを聞いてくれないんだろう」ということが多いように思います。
子どもを怒ってばかりで自己嫌悪になっているお母さんにおすすめの本を紹介します。
2歳~小学生低学年くらいに使えるテクニックが、35の具体例を通して紹介されています。
子どもの自己肯定感・自己受容感を養って、イライラママ・ガミガミママから卒業しませんか?
私が取り入れたいコーチング術・取り入れたかったを紹介します。
この本はKindle Unlimitedで読むことができます。(2024年3月8日現在)

この本はAudibleで聴くことができます。(2024年3月8日現在)

子どもと一緒にココロ貯金について考えるために、一緒に本を読んでみてはいかがでしょうか?
相手の気持ちを考えて行動することの大切さがわかる、素敵な本です。
子どものココロ貯金の増やし方
コーチングを始める前に、「プラスのふれあい」で無条件の愛情を表現することで、子どもの自己肯定感、自己受容感を養うこと重要なのだそうです。
子どものココロ貯金を増やす方法が紹介されています。
魔法の言葉
- ママは、あなたが大好きよ
- ママは、あなたの味方よ
- 生れてきてくれて、ありがとう
恥ずかしくて言いにくい言葉ですが、朝起きたとき「大好きな〇〇ちゃん、おはよう」、夜寝るとき「大好きな〇〇ちゃん、おやすみ」と言うのを習慣にしてはどうでしょうか?
また、子どもが「ママ、大好き」と言ってくれたときはチャンスです。「ママも大好きだよ」と伝えましょう。
プラスのふれあい(カラダへのアプローチ)
- 手をつなぐ
- 頭をなでる
- 身体をくっつける
- 膝に座らせる
- 抱っこする
私は、出かけるときは「いってらっしゃい」と言うときにハイタッチすることにしています。
寝る前は、おやすみハグをしてから眠ります。
子どもが本を読むのが好きなので、ソファーでくっついて読書をしているときが多いです。
プラスのふれあい(ココロへのアプローチ)
- 子どもの話をよく聞く
- うなずく
- 名前を呼ぶ
- 挨拶をする
- 見守る
- 信頼してまかせる
- 感謝をする
マイナスのふれあい
- 軽くたたく、軽く押す
- 叱る
- 注意する
ココロ貯金が外にもれるもの
- 暴力をふるう
- 虐待
- イヤミを言う
- 皮肉を言う
- けなす
- 無視をする
子どもは、怒ってもケロっとしていて忘れる力・許す力がある気がします。
ただ、強度のストレスを感じるとトラウマになることがあります。
長男は、食事中に肘をついてしまうことがよくありました。主人はそれが気に食わなかったので、食事中長男を注視して、肘をついたらすぐに無言で正していたときがあります。
「食事が楽しくなくなるからやめて」と言いましたが、やめて欲しいと頼みましたがやめてくれなかったので、別々に食べることになりました。
もう4年ほど経ちましたが、長男はいまだに「一生一緒に食べたくない」と言います。一緒に食べるのは家族の誕生日に外食する年4回だけです。
「ココロ貯金が外にもれる行動」は子どもにトラウマを与えてしまうため、注意が必要ですね。
怒らないママになるルール
- 子どもを変えようとはせず、ママ自身の行動を変える
- 言葉は短く・肯定語で・わかりやすく
- 子どもがダダをこねているときは、「オウム返し」しながら気持ちをおちつかせる
- 「ココロ貯金」を1日3つトライする
- 怒らないという我慢をやめて、怒らずにする工夫をする
アドラー心理学に通じるものがありますね。子どもであっても、他人は変えれない。自分自身が変わり、コーチング術を使うことで、子どもにいい影響を与えられるといいですね。
子育てコーチング
すぐに口答えをする子には「カッコイイ!」を効果的に使う
やって当たり前なことでも、普段なかなかできないことがすぐにできたときは、
「もう手を洗ったの?カッコイイな!」
「もう布団畳んだの?カッコイイな!」
「もう宿題するの?カッコイイな!」
と言葉で認めていくといいそうです。
また、子どもの反抗的な言い方に腹が立ったときは、「そんな言い方をするものではありません」と厳しく叱るより、「それはないよね~」と軽くかわす方法がいいそうです。
私はよく「ママのせいで忘れ物をした」「ママのせいで早起きできなかった」などと言われて、叱ってしまうことがあります。
これからは、「そんなことを言われると、ママは悲しいな」とわたしメッセージで伝えていきたいと思います。
忘れ物が多い子には準備しやすい環境づくりを
- 時間割とは別に、毎日の定番・毎週の定番の一覧表を壁に貼る
- 時間割タイムを決める
- ときどき必要なものは玄関に置く
- 忘れそうなものは何度も声掛けをする
わが家では、1年生まで毎日の持ち物・週明けの持ち物の一覧表を貼っていました。
毎日
- 筆箱(えんぴつ4本・赤えんぴつ・定規・消しゴム・かきかたえんぴつ)
- 下敷き
- 水筒
- 給食セット(コップ・ナフキン・マスク)
週明け
- 給食着セット
- 体操服セット
- 上履き
水筒と傘は忘れやすいので、玄関に置いています。
いつまでもチェックをしてもらえると思っていると自立心が育たないと思い、2年生になってからは声かけだけにしています。
自分で用意できるかは個人差が大きいので、子どもの様子を見て判断できるといいですね。うちは長男は年長、次男は小2から自分で用意をしています。
小学校に行きしぶる子には言葉と行動でママの愛情を伝える
ママが小学校に送っていったり、家に帰ってきてからのお楽しみを提案するなどの後押しをすることで、子どもが行くことができるようだったら、登校を促したほうがいいそうです。
我が家でも、次男は学校に行くのを嫌がることがあります。子どもが希望するときは一緒に学校まで送っています。すると、周りの雰囲気もあってすんなり学校に行けることが多いです。
子どもの不安をできるだけなくすことが大事だな、と感じました。次男の場合は話すことが苦手で、先生にうまく説明できずに怒られることを恐れている節があったので、本人の不安に思うことは連絡帳に書いて先生に伝えるようにしていました。
また、どうしても行きたくないというときは、休ませたときが何度かあります。1日家で一緒に遊びつくすと、次の日には何ごともなかったかのように学校に行きました。
勉強に集中できない子にはささやき作戦で後押しする
- 帰宅後にプラスのふれあい作戦
- 小さい声で「頑張ってるね」「早いね」とささやく
宿題をするのは1年生には大変なことです。みんなで一緒に勉強をすると進むことが多いです。(長男・次男は宿題、私は資格の勉強をしてます。)
やる気がわかないときは、先にボードゲームや読書をして、夕飯までにできたらOKにしています。
テレビゲームは「宿題が終わってから」というルールがあるので、頑張ってすることが増えました。
1年生のうちは宿題をするのに1~2時間かかることもありました。グルグル回りながら話し続けていたり、壁を登りだしたりして、なかなか終わらなかったですが、だんだん習慣化されて、1年生の3学期くらいから、20分くらいでできるようになりました。
見守っていれば、いつかできるようになるので、是非待ってあげてくださいね。
食べ物の好き嫌いが多い子は長い目で見る
- あらかじめ子どもが食べられる量を考えて器に盛りつける
- 苦手な食材は、長期戦で少しずつ食べる量を増やしていく
うちの次男は偏食で、食べられないものが多いです。2歳のときは蒸しパンしか食べなくなりました。幼稚園まで肉も魚もほとんど食べませんでした。高野豆腐とカニカマばかり食べていました。
給食を完食できるか不安だったのですが、杞憂に終わりました。量を減らしてもらうことはあっても、頑張って食べています。
いろんな食べ物に挑戦することで、食べれるものが増えました。肉や一部の煮魚が食べれるようになりました。今も食べられない食べ物は多いですが、急成長を遂げています。
長期戦で見守ってあげることの重要性を感じました。
わが家では私のストレスを減らすため、次男が食べられるメニューを中心に献立を立て、気に入った給食があればメニューに取り入れるようにしています。
次男が食べられないメニューのときは、代わりのものを出すようにしてます。(冷凍のトンカツ、コロッケなど)
以上、『男の子のやる気を伸ばす お母さんの子育てコーチング術』の紹介でした。
まだまだたくさんのコーチング術が学べます。できることから取り入れて、一緒にイライラママ・ガミガミママを卒業しましょう。
少しでも参考になれば嬉しいです。
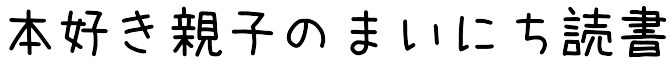
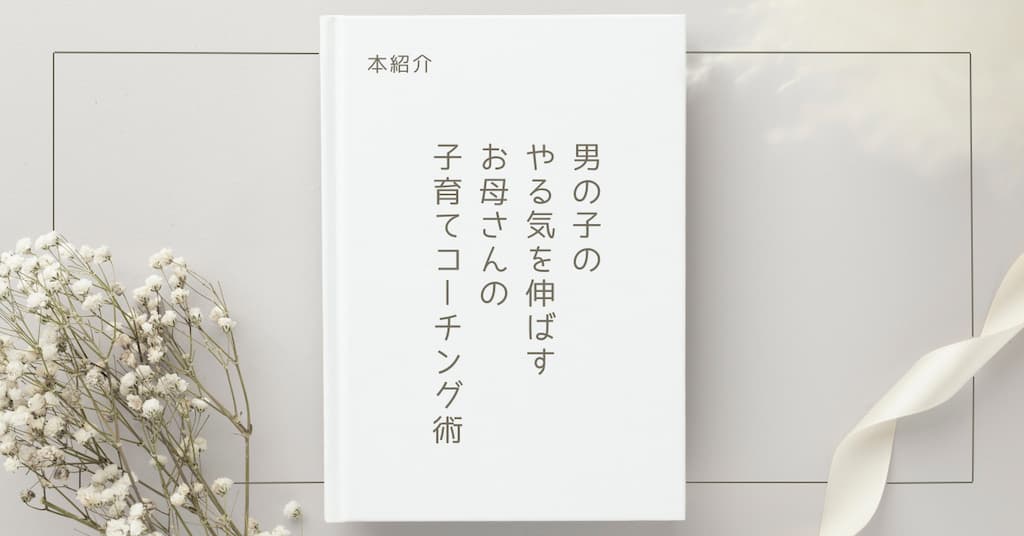





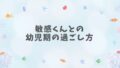
コメント