※この記事はアフィリエイト広告を利用しています。

子どもに自信を持ってほしい!
そんな悩みの解決のヒントをくれる本を紹介します。
次男の自己肯定感が低いことから参考になることがあればと思い読みました。
子どものほめ方、子どもとの関わり方が具体例と共に紹介されています。
私が取り入れた「自己肯定感育成方法」を紹介します。
この本はオーディブルで聴くことができます。

兄弟・友だち・昔の自分と比べない
他人ではなく「ちょっと前の子ども」と比べるといいそうです。
子どもは日々成長しているので、よく観察することが必要だと感じました。
我が家の長男・次男は長所が違い過ぎるため、得意なことが違っていておもしろいね、と伝えています。
親の失敗話を話す
私は自分の失敗話をよくします。
よく落とし物をするので、その体験談を話したり解決法を一緒に考えてもらいます。
買い物に行って、買い忘れをしたときは、子どもに素直に謝ります。
私は大きな失敗をすると1週間くらい落ち込んでいるので、子どもが励ましてくれます。
自己主張をできない子には、自己主張をする練習をさせる
次男が自己主張が激しく、自分の思う通りにならないと癇癪を起すことがあります。
そのため、長男が委縮して自己主張ができないようになっていました。
「自分のやりたいことがあるときは、ちゃんと言わないとわからないよ」と何度も伝えました。
最初は伝えるのが難しかったようで、トラブルになることもありました。
「あと〇回ゲームをしたら、(長男の)やりたいことをするよ」
「〇時からは、(長男の)やりたいことをするよ」
と言えるようになり、トラブルになることが減りました。
子どもにとっての「安全基地」を作る
無条件に「あなたがいてくれて嬉しい」と思える安全基地になることが重要
子どもがまだ喜んでくれるので、ハグして大好きだと伝えています。
ほめるときも、結果ではなく努力した過程を褒めるように気をつけています。
子どもの「好き」は自己肯定感を上げる
我が家ではポケモンが大ブームです。
ポケモンを毎日見るだけではなく、自分でオリジナルのポケモンを考えてポケモン図鑑を作ったり、すごろくやカードゲームを作ったりしています。
好きなことをしているときは、本当に生き生きとしています。
本書で紹介されている「好きなものファイル」を実践すると、楽しそうにお気に入りを集めています。
1週間のスケジュールに必ず「余白」を作る
我が家では子どもたちが希望しないため、習い事はしていません。
ゲーム感覚で学べる「シンクシンク」と、ドリルを1週間10ページ以上と決めて勉強させています。
毎日余白があるので、好きなことに打ち込んで楽しく過ごしています。
私自身は毎日習い事に行って忙しく過ごしました。
しかし、習い事にお金を掛けたことで、私立大学に行く余裕がなく、進学先が制限されました。
大学進学時に金銭面で諦めさせたくないので、習い事にお金をかけないことにしました。
子どもが本当にやりたいことだけやらせよう、と思っています。
以上、私が実践した「自己肯定感育成方法」でした。
今日も一歩前進です!
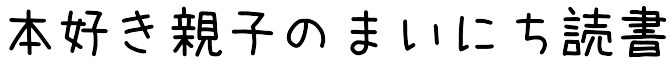
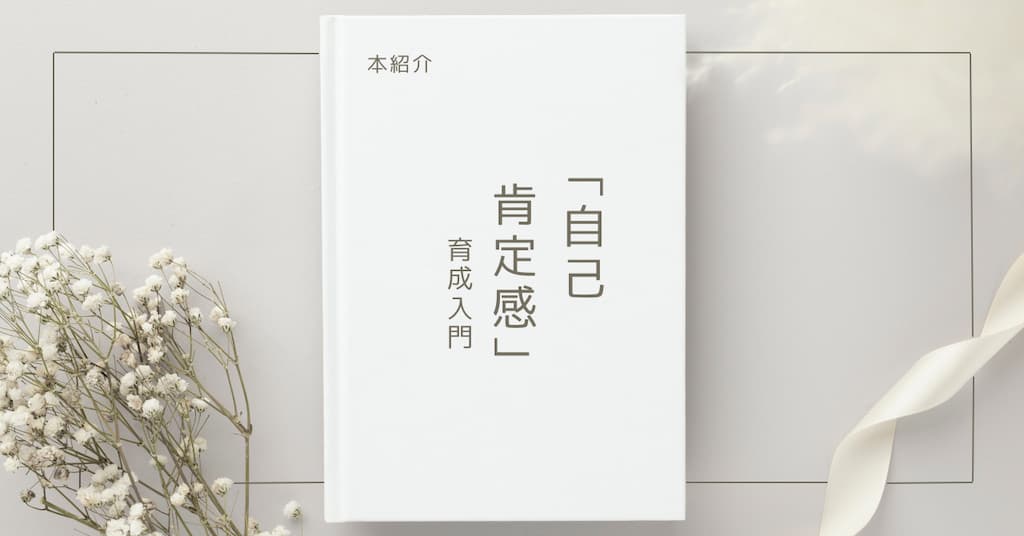


コメント